腸全体の特徴
腸の仕事は、食べ物を消化していくことです。
口、喉、食道、胃、腸、肛門、から構成された全長9m前後にもなる1本の長い消化管のうち、腸は3分の2以上を占める7~9mになります。この長い管を通じて、食道・胃を経由してきた食べ物の栄養を吸収していくのが小腸です。小腸の腸壁で栄養が吸収されたあと、大腸に送られます。大腸に送られる食べ物はすでに栄養素が吸収されたあとですが、大腸でも一部の栄養素と水分が吸収されていきます。大腸での吸収作業が終わった後に残ったものは、便として体の外に排出されていくことになります。
このように、腸は体の中にありながら体外と関わる場所のため、別名「内なる外」と呼ばれることもあります。
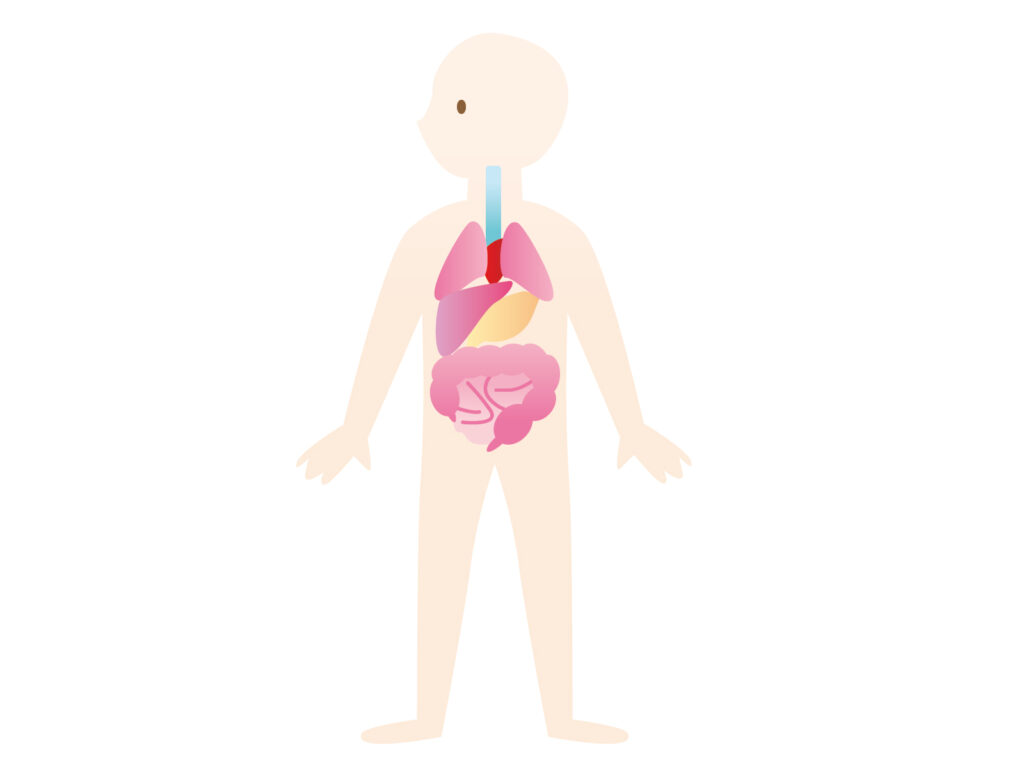
病原体はウイルスや細菌といった私達の健康に害をなす存在です。腸は「内なる外」と呼ばれるように、外から入ってきたものが通過する器官ですから、食べ物と一緒に病原体が入り易いのです。
そのため、腸は他の臓器よりも防御機能が発達していて、全体の3分の2に相当する免疫細胞が腸にはあります。腸は免疫の要なのです。
神経細胞が最も多いのは脳です。そして次に多いのが腸のため、第二の脳と呼ばれています。腸はたとえ脳死状態になったとしても呼吸と血液の循環があれば、独自で栄養分の吸収や排泄が行えます。それに対して脳は必要とする栄養分の吸収口を全て腸に依存しているため、腸が機能停止してしまえば脳は何も出来ないのです。腸は第二の脳と呼ばれていますが、脳に依存せずに自律している脳に負けない凄い臓器であることがおわかりいただけたでしょうか。
小腸の特徴
小腸は約5~7m(実際には縮んだ状態で約3mほどに収まっている)ほどの長さを誇る臓器です。小腸には栄養素を吸収する絨毛(じゅうもう)と呼ばれる突起物に覆われていて、表面積はテニスコート1~2面分にもなると言われています。小腸は長く毛深く、そして広い表面積を持つのです。
絨毛は1mmに満たない突起物ですが、ここから体に必要な栄養素が吸収され毛細血管に溶け込み、門脈と呼ばれる消化器系特有の血管を通って肝臓、そして全身へと送られます。
小腸は絨毛に覆われているのには理由があります。絨毛を増やして毛深くすることで表面積を増やし、小腸を通過する食べ物との接触面を増やすことができるためです。接触面が増えれば体に必要な栄養分や水分を無駄なく効率的に吸収できます。飽食の現代にとってはあまり必要ないかもしれませんが、昔は食べ物が少なかったため、生き残るためにはいかに少ない食べ物を無駄なく体に摂り込めるかが生きるために重要だったのです。小腸の長さと毛深さは、生き延びるために発達した能力と言えます。
また、小腸は毛細血管が多いため、消化器の中で最も血液が必要とされており、全体の30%にも及ぶ血液が使用されます。第2位が腎臓で20%、続いて脳と骨格の筋肉がそれぞれ15%と続きます。小腸が血液をたくさん必要とするということは、小腸の血液循環が良くなれば全身の血行も促進されて体全体が温まって代謝がアップするということを意味するのです。
大腸の特徴
大腸は管の直径5~7cm、長さは小腸より短く約1.5~1.6mです。小腸ほどの伸縮性はなく、ツルツルで毛深くありません。小腸と肛門の間に位置し、小腸と大腸の境目には逆流を防ぐ弁があるため一方通行になっています。食べたものは小腸と大腸の境目にある弁の前後で呼び方が変わります。小腸では栄養素と呼ばれますが、大腸では便となります。
大腸の役割は、小腸で吸収されなかった残りの水分の吸収を行い、食べ物のカスや食物繊維、腸壁の老廃物などを原料に便を作ることです。便を肛門まで輸送する過程では、腸壁に傷がつかないよう粘液をたくさん分泌し、粘膜で覆って腸管内を保護しています。
腸内細菌の多くが大腸に住んでいます。腸内細菌には、大腸に送られ内容物分解して便にする力があるほか、体に必要なエネルギーに再利用できる発酵させる力を持っています。本来捨てられるものを元にアミノ酸や脂肪酸、酪酸、酢酸、ビタミンB群、ビタミンKなどを作ってくれるのです。
便というとただの廃棄物、というイメージですが、大腸を通っている間の便はまだまだ利用できるところがあり、大腸が無駄なく再利用してくれているということになります。水分を吸収するだけでないので、良い便作りには腸内細菌の力が必要不可欠であると言えます。
ですが、1点問題があり、エネルギーの再利用をする際にガスが生じます。ガスが生じること自体はごく普通のことなのですが、悪いガスが溜まってしまうことが問題を引き起こすことがあります。臭いおならが出たり、腹の張りや痛みといった症状で、「お腹が張っている」という感覚はこの状態であることも多いです。
この解決策の一つが腸揉みです。腸揉みすることによって溜まった悪いガスを流していくことが可能になります。悪いガスが溜まってしまう原因には、過度な緊張状態の連続により交感神経が強まったときや腸内細菌のバランスが崩れることが挙げられます。
ここまでで腸の基本を学習してきました。
次は最後に挙げた腸揉みについて詳しくみていきましょう。