腸内細菌
腸内には多くの細菌が住んでいます。この細菌を腸内細菌と呼びます。前の章でご紹介したように、便の固形成分の3分の1を占めるのがこの腸内細菌またはその死骸です。腸内細菌は小腸の終わりから大腸にかけて、種類ごとにまとまり腸内に壁面を作って生息しています。
この様子が植物が群生している花畑のように見えることから腸内フローラと呼ばれています。テレビCMなどでもおなじみのキーワードですね。腸内細菌の種類や数は、食生活や生活習慣、人種、年齢などによって異なるため、腸内フローラの状態は人によって異なります。
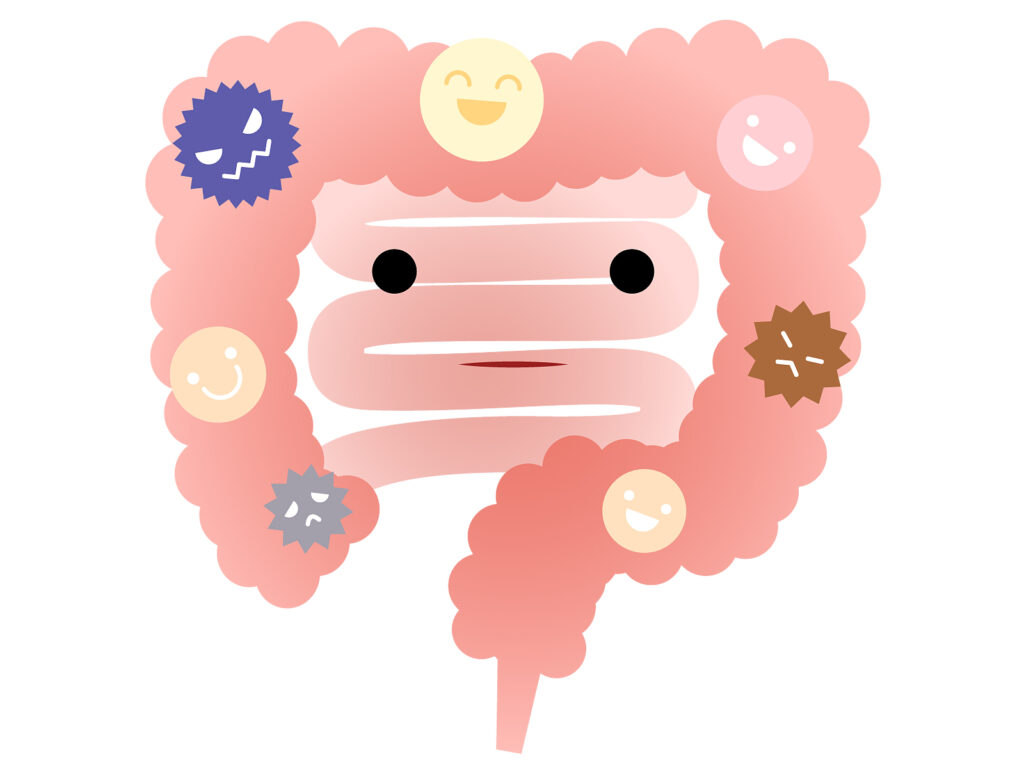
腸内細菌は1日に必要なエネルギーの10%を作ったり、胃や腸が消化出来なかったものを消化してくれたりと私達を助けてくれる大切な存在です。他にも免疫を高めたり、感染を予防してくれたりします。
腸内細菌の分類
腸内細菌は働きの種類から大きく3つに分類することが出来ます。人の体に有用な働きをする善玉菌、有毒物作る悪玉菌、そして善玉菌でも悪玉菌でも無い日和見菌の3種類です。日和見菌は善玉菌と悪玉菌の優勢な方に味方する菌で、どっちつかずの菌ということですね。
健康な人の腸内は善玉菌が悪玉菌を抑える形で腸内フローラのバランスが維持されていますが、何らかの原因で悪玉菌が優勢になったときバランスが崩れ様々な異常を起こしてしまいます。
悪玉菌が優勢になると、便秘や下痢という腹の症状、免疫機能低下により腸だけでなく全身の感染症を起こしやすくなったり、腸内腐敗が進んでアンモニア、フェノール、インドールなど有害な物質が増えます。これらが臭いおならの原因になったり、肝臓、心臓、腎臓などにも負担を与え、老化を促進させたり、生活習慣病の原因になることもあります。
腸内の細菌は平和に共存しているわけではありません。機会があればすぐに勢力を拡大しようと戦っています。善玉菌と悪玉菌だけでなく、違う種類の善玉菌同士や、悪玉菌同士が戦うこともあります。これにより、善玉菌が増えると悪玉菌は減り、悪玉菌が増えると善玉菌は減っていくのです。
ただ、注意したいのは「悪玉菌=絶対にいないほうがいい害のある菌」というわけではない点です。悪玉菌は人間にとってよくない働きをすることが多いので悪玉菌という呼び名がついていますが、必要な働きもあると考えられています。
ですから、健康な腸にするためにはバランスを保つことが大切で、理想的割合は善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割と言われています。
このバランスは年齢や食生活、ストレス、薬の服用などが影響し日々変化していますので、たんぱく質を過剰摂取しない、ストレスを避ける….など、対策をしていくことが肝心です。